<原点回帰の中央線……私の最後の作品?>
 |
11月30日、朝早く山田玲二画伯が絵の具を持って現れて、この「絶望から希望へ…」のテーマに沿って大作を数時間で書き上げた。山田氏も満足風で出来上がったものをカメラに納めた。そして私も大満足で絶賛した。ありがとう山田画伯。 |
昨年の春、ふっと私は今、30代後半のシラケ世代の多くが陥っているという「自分探しの旅」がしたくなった。60歳を過ぎた自分の「立ち位置」、「自分は今どこにいるのか? そしてさらなる老いに向かってどこに行こうとしているのか」を、無性に確認したくなった。私が愛する新宿歌舞伎町も、監視カメラに24時間体制で見張られ、有名チェーン店が並ぶだけの画一化されたつまらない町になってゆきつつある。1976年に新宿LOFTをオープンしてからもう30数年、今やヘッドオフィスと3軒の店がある新宿に棲息するも、どこか息苦しくなっていた。もう長いこと、「自分が本当に楽しめる最後の空間を構えるとしたら、どこの場所にしようか」と考えていた。やはり「土着化」をはかるなら、巨大ターミナル駅でも、今流行の秋葉原でも、銀座でも六本木でもないな〜と思っていた。
 |
この壁の古い板はアメリカ南部の200年前の古屋を解体したもの。普通の古材ではこの色は出ない。カウンターの上には本物の鉄を巻いたやはり100年以上前の荷馬車の車輪が吊ってある。是非ごらんあれ。カウンターの青色は、白木の分厚い一枚板にペンキ屋がぽったっと一滴間違えてしずくを落とした。それがあまりにも良い色をしていたので、即決して蒼いカウンターになった |
そんな時、何となく「中央線文化」というテーマがひっかかったのだ。「ロフトの平野は文化を発掘するなんて言って、また金儲けに走っている」なんて評判が聞こえてきそうだが、もう私には名誉とか金儲けは興味がない。そんなことに執着する年代でもない。かつて私が若者だった頃、私たちの前の世代は、あの悲惨な戦争をやってきた連中だった。そういう権力者がまだこの社会を牛耳っているのを「老害」と切り捨てていた。「時代はいつだって若者のものだ。お前達はステージから去れ!」って叫んでいたのだ。
<阿佐ヶ谷ロフトA 2007年12月1日なんとかオープン!>
 |
ここに並ぶお方達はロフト35年の歴史の恩人たちである。酒癖悪いけど、感謝しています。左から仲野茂(アナーキー)、下山淳(ex.ルースターズ)、某映画監督、ジョー(G.D.フリッカーズ)、池畑潤二(ex.ルースターズ)、キース(ex.ARB) |
12月1日、ついに中央線阿佐谷駅にトーク系ライブハウス「阿佐ヶ谷ロフトA」がオープンした。
阿佐ヶ谷ロフトAのステージの壁絵は、「絶望に効くクスリ」(小学館『ヤングサンデー』連載)の著者、山田玲司画伯にお願いした。この壮大な「壁絵」をぜひ見に来て欲しい。コンセプトは「絶望から希望へ……」。こんなテーマの店ってあったかな? この店のメッセージには、80年代初頭の「パンク日本上陸」で私が受けた衝撃、「現実から逃げない……そう、現実は戦争や暴力、貧富の差、不正と欺瞞で満ちあふれているじゃないか? 素晴らしい世の中、素敵な人生なんかありゃ〜しないんだ!」という若い連中の雄叫びが内在している。
 |
階段を下りて、入り口に向かうと、洋風なおしゃれなバーがあって、そ このキャッシャーが鉄格子と斧とピストルがお迎えする。怖いですね。
|
私は今もあの絶望的な時代……、そう、80年代の怒濤のようなパンクロックの進撃を夢見る。
簡単なコード、リズムは性急、へたくそで乱暴、その早いサウンドはより現状の切実さを感じさせるものであった。当時のパンクの最大の意義は、過去のものをきっぱり否定したことだ。「俺たちは俺たちのやり方でやる」といった刹那性、自分でももてあますような感情の揺れやブレが、すさまじい形で表現されていった。
今回の私の挑戦にもまた、そういうスリルがたくさんあった。どういう空間作りをしたら、今の若者達の「感情の揺れやブレ」を表現できるかを考え込んだ。人間、何かやるとき、つまり「決起」するには色々悩んだり、緊張したり、心配したり、躊躇したりあきらめたりもする。決めたことを計画通りにちゃんとやらないでいいのかも知れない。未来のための積み重ねである必要もないのかも知れない。そんなことは、逃げないで現実と向き合って体験してみないと、絶対わからないのだと思う。重要なのは、今起こっていることが現実の出発点で、たくましく希望に向かって歩いて行こうということ。それが阿佐ヶ谷ロフトAのイメージなのだ。
 |
ネオン写真……昭和のレトロな町阿佐ヶ谷に、おしゃれなネオンもついた。何ともロフトらしからぬネオンだ。キャバレーか? こんなネオン、パール商店街にはなかったな。ネオンは値段が高いからか(笑)? |
阿佐ヶ谷ロフトAが開店しもう半月が過ぎた。季節はもう師走なのだ。この小誌が出るのは年が明けてからなのだが、今私はこの原稿を書きながら「師走」を考えている。師走ってなにか、1年の終わりの感激深い雰囲気が醸し出される。1年間のするべきことを終え、その年を懐かしく思い、新しい年を迎える。町の街路樹の木の葉が落ちて寒々しい木立が並び始めた。そんな隙間から、青い真冬の空がすけて見えた。
今月の米子じゃなくってO君★
今月の米子、じゃなくってO君。ペットのコジマ生まれの2歳。スコティッシュ・ホールド……耳がたれている猫はこの種類だけらしい。突然変異だそうなんだ。耳の隙間にダニがたまるそうだ。私の還暦祝いに105,000円で買った……で、米子と違って「猫なべ」が大好きなのを発見した。素晴らしい。
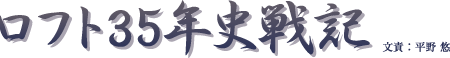
ロフト35年史戦記・後編 第34回 新宿ロフトプラスワン編−1(1995年〜)
新宿LOFTが新宿西口から歌舞伎町のど真ん中に移転して10年近くなる。もうロフト移転の戦いは過去のものとなり、日本のロックの一つの伝説になろうとしているのだろう。だから現在のスリリングな歌舞伎町ロフトしか知らない表現者がどんどん多くなって来ている。
西荻ロフト時代の常連であり、ロフトを法律面でサポートしてくれている青山力弁護士に、立ち退き騒動から最終的な移転に至るまで、裁判の顛末を聞いてきた。この「ロフト立ち退きの戦い」の記録をあえて長々と書き続けたのも、今回が最終章になる。
この一連の戦いの流れの中でロフトは、なにごとにも「長いものには巻かれろ」的な発想のいわゆるあきらめ系の若者達に対して、「戦えば道は開ける」「決してあきらめてはダメだ」という、私が信じる「ロックスピリッツ」を表現したかったのかも知れない。(構成:今田 壮)
<戦いすんで日が暮れて……>
今から3年も前になるだろうか? かの有名なスキャンダル雑誌『噂の真相』が、岡留安則編集長の独断と偏見により黒字のまま廃刊となり、『『噂の真相』25年戦記』(集英社新書/05年)というカリスマ編集長が書いた単行本が出版された。それを読んだ私は、「そうか? 『噂の真相』の歴史が25年なら、ライブハウスロフトの歴史はもう足かけ35年にもなるな。面白くなるかどうかわからないけれど、自分もロフトの歴史でも書いてみるか?」と思い立った。
それが、この連載を始める発端だった。
私が一番書きたかったのは、ライブハウスロフトの創世記(1972〜1980年)と、新宿LOFT立ち退きの戦いのことだったが、その話は一応、昨年までで終わった。
 |
ロフトプラスワンオープンを告げるチラシ。「突然何かに出会ってしまう空間」とのキャッチフレーズの通り、数々の「事件」が起こるのだが…… |
<立ち退き問題が勝利に終わって……>
さて、私の人生後半の「戦い」は本質的には、ここから始まったのだと思っている。
というのは、新宿LOFT立ち退き裁判は、相手から仕掛けられたものであり、私が日本に10年ぶりに帰国して初めての仕事であり、いわゆる「売られた喧嘩は受けて立つ」といった不可避的な戦いだった。幸か不幸か、ロフト再入居避難のための場所としてオープンした下北沢SHELTERの営業成績も、その独自な戦略がうまくいって順調だった。
しかし個人的には、問題は別のところにあった。私のロフトでの「居場所」がどこにもないのだ。当時の私に、立ち退きの戦いは出来ても、日本のロックをにわかに理解出来るわけはなかったのだ。だから相変わらず、日本のロック状況には「浦島太郎状態」が続いていた。かの日本のロックシーンを根底から変えてしまったという大ブレイクバンド、BOφWYすら理解出来ない状況で、ロフトに行っても面白くも何ともなかった。日本に帰ってもう一度ロックシーンの最前線に戻り、ロックのオピニオンリーダーとして刺激的な毎日を過ごしたいといった夢は、見事に自らの硬直した頭とフットワークの悪さにパンクする有様だった。
ロフトは長いこと日本のロックの中心であり続けていたのだが、いくら私が頑張ってみても、そこにある音楽性、ロックビジネスのあり方、そこに依拠する自称ロック人達を含めて、私にとって理解賛同するには全く無理な事であると実感していた。それほど、日本のロック業界は巨大なマネーゲームの資本の論理にすっぽりはまりこんだアメーバーのようだったのだ。当時の私は、そのことをひしひしと感じていた。
<変貌してしまっていた日本のロック業界>
 |
新宿厚生年金会館のさらに先、新宿富久町のほとんど四ッ谷に近い雑居ビルの1階にかつてのプラスワンはあった。細長い廊下の向こう、雑然としたビラの合間を抜けると店内 |
すなわち、日本のロック状況は、私が日本を発った10年前とは一変していたのだ。ロフトに出演するバンドは、そのほとんどにプロダクション、メジャーレコード会社がついており、マネージャーが、ファンクラブが、PAオペレーターが付き、商売の為のシステムがきっちり出来上がっていた。
そのミュージシャンを売るために血眼になっているスタッフを見ていると、目眩がしてくるくらいみんな真剣だった。とても過去、荻窪ロフトや下北沢ロフトでやっていたような、「ロックって楽しいね!」なんて雰囲気ではなかった。日本のロックは「一部不良の音楽」ではなくなっており、ビートルズが教科書に載る時代になってしまっていた。ロックは確実に市民権を獲得し、それまでメインカルチャーだった「歌謡曲」を凌駕する存在になっていて、それはすなわち大資本の論理(利益至上主義)の射程距離に入ってしまっていたということだった。
だからといって、今あるロフトを全く自分の好みの店に変えるわけにも行かず、私は何もするべきことがなかった。昔のようにお客さんや出演者とわいわい適当にやりながら何かを作っていく、そんな店とお客さんと出演者の「共同作業の場」としてのライブハウスは無くなってしまっていた。
多くの出演者にとって、ロフトのような小さなライブハウスは、パワステやオンエアのようなカップラーメン屋や大手不動産屋など大資本が経営している大型「ライブハウス」、さらには渋谷公会堂、武道館というホールへステップアップするための、一時的な小屋でしかなくなっていたのだった。売れていないときは出演してくれるが、売れ始めると小さなライブハウスは見向きもされなかった。何度も書くが、小資本のライブハウス経営の一番の悲しさは、せっかく駆け出しの頃から応援してきたバンドが、人気が出ると出演してくれないということだった。そうなると、ライブハウス側にとっては、出演してくれているバンドはブレイクしないでくれた方がいいのだ。これは仕事としては絶望的だな、と思った。
 |
初日の一日店長はご存じキースさん。以来、ロフトプラスワン歌舞伎町リニューアルオープン、Naked Loft、阿佐ヶ谷ロフトAと、ロフトのスタートはいつもキースさんから |
結果、ライブハウスはあの悪名高き「ノルマ制」という自衛手段を採用することになる。自分の店に出演してくれるバンドを応援していて、しかし仕事としては売れない方がいいなんて思ってしまうという、なんとも馬鹿な業界に見えた。
<自分の居場所探しの旅……トークライブハウスの着想はここから生まれた>
私はあせっていた。1995年春、新宿LOFTの立ち退き裁判が、再入居前提の和解成立ということでとりあえず一段落し、毎日毎日無為に時間を浪費していた。私が現実のロックのライブハウスにどんな意見を言っても通用せず、必要とされていないことを痛感していた。私はロフトの社長をも辞める決心もしていた。
社長なんていう地位には興味はなく、ただ何とか自分の居場所が欲しかった。あのキラキラと輝いていた青春時代の高揚を、もう一度復元したかった。私はすでに50歳になろうとしていた。私はもう一度、「日本を捨てて海外に出るか?」と真剣に悩んでいた。
ある小さな居酒屋で一人飲んでいた時のことだった。大雪の降りしきる夜だった。居酒屋は意外と混雑していた。私の隣の席では、中年の男女が写真を並べながら、それは一生懸命「生け花と盆栽」の話をしていた。
「生け花ってのはなあ、全てに花鳥風月ていう表現があってさぁ」という話から始まって、私はいつの間にかその話題に引き込まれ、初対面のその男女に、思わず色々な質問をしてしまっていた。話題は日本の古典文化の話になり、カウンターの中の店のオヤジまで入ってきて、「日本の祭り」の話になった。そこのオヤジの本職は、もう日本では何人といなくなってしまった「祭り職人」だったのだ。このオヤジの話も面白かった。
生け花の話も、祭りの由緒正しい伝統的な格式の話も、ほとんど初めて聞く話だった。しかも、ふらっと入った居酒屋で酒を飲みながら、自分の知らない世界を聞くことの面白さを知った。町の片隅には、それぞれ色々なこだわりを持って生きている無名の人達が沢山いるんだ、と実感した。それは過去、名も知らないバンドの演奏と出会って、「感動」してしまう時の「一期一会」の感覚のように感じられた。
ふっと私は、こんな居酒屋を作ってみたくなった。ふらっと入った居酒屋で、自分の知らない「こだわりを持った人」の話を聞く。今までそんな居酒屋が存在していただろうか? 世間の面白そうな人達を招いて、その人が何十年にもわたってこだわり続けてきた、いぶし銀の世界をかいま見る。そんな空間があったら面白いと瞬間的に思った。私が挑戦する価値は充分あるように感じられた。
 |
座敷に神棚、このへんの空間作りのこだわりもこの頃から変わらない |
幸いにも私は20数年間のライブハウス経営の蓄積がある。
私がライブハウスを始めた1970年代前半には、東京ではロックを生で聞ける店は皆無だった。まだ『シティロード』とか『ぴあ』なんていう情報誌もなかったし、「ライブハウス」なんて言葉すら無かった時代だ。ライブに集まる客も、多くて50〜100人ぐらいだったのだ。当然やる方も見に来てくれるだけで幸せだった。店を維持するには、ライブの始まる前はロック喫茶でコーヒーを売り、5時半からリハーサル、6時半客入れ、7時本番、夜10時頃にライブが終わると、急いで店を片付け、それから店は朝4時まで居酒屋で酒を売る。だから店側はライブで飯を食うという発想は全くなかった。毎日が楽しすぎた。
「そうだ! 俺が一番最初やったライブハウスの原点に帰れば、なんとかなるかも知れない」と思った。世界初の「トークライブハウス」の構想は限りなくふくらんでいった。
この新たな私の挑戦を前に、私はロフトの社長の地位を、若手の小林茂明現社長に譲る決心をした。それ以降10年ばかり、私は「トークライブハウス・ロフトプラスワン」に全精力を傾けることになる。
<プラスワンのスタートとオタクの人たちの登場>
誕生したばかりの新宿ロフトプラスワンは、ブッキングも宣伝も、困難を極めた。
まだインターネットで情報を告知出来るシステムはなかった。当時数あった情報誌関係にも、スケジュール掲載を断られた。私たちスタッフは、出演者(一日店長と呼んでいた)から住所録をもらい、出演者の知人、縁者にDMを出したりして、トークライブを見に来てくれる人を確保もした。
 |
ステージからの眺め。正面のカウンター席がいかに近いかよく分かる |
そんな中、この奇妙な空間にとても興味を持ってくれている塊があった。それは今や世界共通語になってしまったが、当時どこか「差別語」として言われていた「オタク」の人たちの存在だった。彼らは多くのネットワークを持っていた。彼らは貴重な映像とか雑誌とかを持って、マクドナルドなんかの2階で、おのおのが収集したものや情報を、見せあったり交換しあったりしていたのだ。その集団がロフトプラスワンという空間を、自分たちのコレクションの発表の場としても利用しだした。この思ってもいない現象に、トークライブハウスという前代未聞のコンセプトを掲げた店は、大いに助けられることになるのだった。(続く)

『ROCK IS LOFT 1976-2006』
(編集:LOFT BOOKS / 発行:ぴあ / 1810円+税)全国書店およびロフトグループ各店舗にて絶賛発売中!!
新宿LOFT 30th Anniversary
http://www.loft-prj.co.jp/LOFT/30th/index.html
ロフト席亭 平野 悠
|
