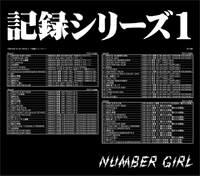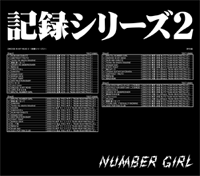|
「第一印象は“ヘンなバンドだなぁ”と」(古閑)
 ──まず、2枚組ベスト『OMOIDE
IN MY HEAD 1 〜BEST&B-SIDES〜』から始まった“omoide in my head project”が始まった経緯から訊かせて下さい。 ──まず、2枚組ベスト『OMOIDE
IN MY HEAD 1 〜BEST&B-SIDES〜』から始まった“omoide in my head project”が始まった経緯から訊かせて下さい。
吉田:ナンバーガールにベスト盤とか企画編集盤みたいなものがそろそろあってもいいんじゃないか?
っていう話が以前から社内でもあったんですよ。でも、中途半端なものを出すのはイヤだなぁと個人的にはずっと思っていて。で、向井君と加茂が話をすることになって、向井君いわく「やってもいいですけど、やるなら徹底的にやって下さい」と。「安易な編集盤ではなく、“ナンバーガールらしいもの”を作って頂きたい」と。スタジオ版のベストだけじゃなく、他にもライヴや映像を録り溜めたものがたくさんあるんだから、それを年間を通
してリリースするくらいの勢いで、って。
吉村:あれでしょ、向井の言葉で言うと「“ガッツリ”したもの」でしょ?
吉田:そうそう、「“ガッツリ”やってもらわなきゃ困るから」っていう(笑)。「当時ナンバーガールに深く関わってきた人がちゃんとやってほしい」と。他のメンバーにも話をしたら、みんな「全然いいっすよ」という返事だったので、今回こうしてプロジェクトとして立ち上げることになったんです。
加茂:向井君も「口は出さない」と。「そっちに任せるから、その代わり半端なものは作るなよ」って言ってくれて。
──今回の『OMOIDE IN MY HEAD 2 〜記録シリーズ〜』は、「『記録シリーズ』をすべて収録したい」という向井さんの強い意向があったそうですね。
吉田:そうなんです。『記録シリーズ』はライヴ会場限定で販売されていたライヴ音源で、計3タイトルあって(カセットが1本、2枚組CDが2タイトル)、それだけでもう5枚組になっちゃうから凄い困りまして(笑)。それだけになるのも何だし、未発表の貴重なライヴ音源は多々あるから、いっそのことBOXにして数セット出そう、ってことになって。
加茂:ここで出しておかないと、次にまたいつ出せるか判らないですからね。
吉田:ナンバーガールには膨大な数のライヴ音源が残ってるんです。4チャンネルだけの、エアーとラインだけで録ってるものも含めたら凄まじい量
になりますよ。割と状態の良いライヴ・レコーディングが大概残っていたので、それをどうまとめようかと苦心しましたね。
吉村:最後の“ナムヘビ”(『NUM-HEAVYMETALLIC』)のツアー全部を『記録シリーズ』で出そうとする幻の企画もあったんでしょ?
吉田:そうですね。ツアーは全部録ってたから、「出そうか?」なんて話もあって。ただ、ライヴは1時間半とか2時間だから、1公演につき2枚組になるんですよ。それが33公演あるから、少なくとも66枚セットにはなるのであえなく断念したんです(笑)。
──その膨大なライヴ録音を聴くだけでも大変な作業ですよね。
吉田:ええ。相当聴き込みましたよ。選曲の基準は、ライヴ演奏や録音状態がいいものを第一条件にして。“ナムヘビ”のツアーは『記録シリーズ』として2タイトル出していたから、それでいいだろうと。今回、『OMOIDE
IN MY HEAD 2 〜記録シリーズ1〜』のほうに収めた名古屋CLUB Rock'n Rollのライヴ('99年9月27日『DISTORTIONAL
DISCHARGER』)とかは凄く面白い掘り出し物で、“こんなの録ってたっけ?”って自分でも忘れてたものも結構ありましたね。
加茂:録音状態が今ひとつでも、ラインだけで録ったCLUB
Queのライヴ('98年6月22日『東京スナック菓子ナイト』、8月23日『VIVA YOUNG!』)は演奏が良かったので例外的に入れましたけどね。
──古閑さんが初めてナンバーガールのライヴを観た時の印象は?
古閑:“変わってるなぁ、ヘンだなぁ”と(笑)。ブッチャーズやイースタンユース、洋楽のいわゆるオルタナに影響を受けたサウンドなんだけど、博多で純粋培養されたような、何か異質なものを感じましたよね。最初の頃は俺、“絶対に売れないだろうな”って思いましたよ(笑)。間違いなくそう思ってた。
──でも、そんな彼らの初のフル・アルバム『SCHOOL GIRL BYE BYE』をK.O.G.A
Recordsから再発したり…。
古閑:それは、僕が彼らと博多や東京でよく呑んで楽しく騒いでいて、彼らが上京するってことでファースト・アルバムがちゃんと流通
されてないって話を聞いたので、「じゃあ、ウチで1枚出したら面白いじゃん」っていう、ある意味軽い気持ちだったんですよ。
加茂:当時、アルバムはあるのに流通
させてもらえない状況があったんですよね。
古閑:そう、そのお陰で一悶着も二悶着もありましたけど…(苦笑)。でも、あそこで諸問題をクリアにして『〜BYE
BYE』を出せたのは繋がりとしても良かったんですよ。だって、その頃はまだ吉村君と今みたいに親しくなかったですもん。吉村君と呑んで喋れるようになったのは、間違いなくナンバーガールの存在があったからですよね。それと…申し訳ないですが、あのアルバムを出したことによって会社としては凄く潤ったので(笑)有り難かったですよ。
吉村:ちなみに、ひさ子はこのBOXにも収められてる新宿JAMのライヴ('99年6月22日『FANCLUB
3』)をカセットに落としたのが今でもお気に入りみたいですよ。「私のギターが大きい」って理由で(笑)。あのカセットのエアーが凄く好きみたいで、このBOXのCDだとちょっと綺麗すぎて、本人いわく「ちょっと違う」らしいですけどね(笑)。
吉田:綺麗に歪みすぎちゃってる感じがあったのかもしれない。マスターは全く同じなんですけどね。確かに、CDになるとちょっと音の質感が変わる感じっていうのはあると思いますけど。僕もJAMの音は「ちょっとヘンじゃない?」ってディレクターに確認しちゃいましたから(笑)。これはマルチで録ってなくて、4チャンだけなんです。エアーとラインをミックスしたもので、奇跡的によく録れたんですよ。
加茂:そのバランスが凄くいいよね。あのJAMのライヴは名演ですよ。あのライヴをCDとして出そうって話もギリギリまで残ってましたからね。
「喉ごし爽やかな“生ビール”みたいだった」(吉村)
 ──吉村さんのナンバーガールとのファースト・コンタクトというのは? ──吉村さんのナンバーガールとのファースト・コンタクトというのは?
吉村:僕らが『未完成』っていうアルバムを作ってる時に自分たちのBBSサイト(ブッチャーズのファン・サイト『サンカクヤマ』)があることを知って、レコーディングの合間にそれを見ていたんですよ。そのサイトを見るっていうよりも、動かし方が判らないから「全部プリント・アウトしてくれ」って頼んで(笑)。で、それを読んでると“ナンバーガール”っていう名前があったんです。ナンバーガールと初めて共演したのは『NHKライブビート』('99年6月3日収録、OAは6月23日)だったのかな。最初はゆらゆら帝国とブッチャーズっていう組み合わせで、ゆら帝はインディーの頃から“スゲェ!”って思ってたから個人的に楽しみにしてたんだけど、メンバーがケガをしてキャンセルになったんですよ。で、“どうしましょう!?”ってことになって、とりあえず『ライブビート』の現場を見学に行くことにしたんです。その時やってたのがポリシックスとボートだった('99年4月29日収録、OAは5月20日)。そこで番組を担当していた沢田太陽さん(現・音楽ライター)に「ナンバーガールって知ってますか?」と訊いたら、「もちろん知ってますよ!」と。それでブッキングをお願いしたんですよね。
──ということは、ナンバーガールの音楽を知らずにブッキングを決めたわけですね。
吉村:うん。その頃はまだ東芝からメジャー盤も出てなかったしね。後で「透明少女」が入ったアドバンスのカセットを貰って“いいバンドだな”って思いましたけど。メンバーと初めて会ったのは、このBOXにあるブックレットによるとSHELTERの古閑さんのイベントですね('99年5月23日『K.O.G.A
presents』)。『ライブビート』で共演するから一人で会いに行ったんです。彼らのライヴを観て駅まで帰ったんだけど、ライヴの印象が強烈に残って、どうしてもメンバーに会いたいと思ってSHELTERに戻ったんです。それが僕の言うところの“生ビール”なんですよ(笑)。
──“生ビール”?(笑)
吉村:凄い暑い日だったっていう記憶があって、生ビールがとにかく旨かった(笑)。
西村:俺もその日に吉村さんに会った記憶がありますね。「あれ、今日はどうしたんですか?」って訊いたら、「ナンバーなんたらがよぉ…」みたいなことを言ってたような(笑)。
吉村:“生ビール”っていうのは、その頃のナンバーガールがそういう音をしていたこともあるんです。何て言うのかな、“炭酸”って言うかな…。
──一口に“炭酸”と言っても、ビールのそれと、清々しいサイダーのような“炭酸”もありますけど…。
吉村:うーん。どっちにしても“炭酸”って言うか…その、細かい泡の粒子って言うか。そういう表現ですね、あのサウンドは。あのサウンドは、向井が作ったもののなかで僕はかなりイケてるなと思うんですよね。
加茂:実はかなり自分流なんですけどね。「透明少女」も『SCHOOL
GIRL DISTORTIONAL ADDICT』も、福岡で友人のエンジニアとアナログ8チャンネル・レコーダーで録ってますから。
吉村:彼らと知り合ってからはライヴによく遊びに行きましたよ。で、そのすぐ後に『RISING
SUN ROCK FESTIVAL』の第1回('99年8月21日)があるんですよね。
──「この曲をやるために帰ってきました」と言って「7月」が演奏された、伝説の名演があった回ですね。
吉田:大トリのサニーデイ・サービスの前、ブッチャーズが真夜中の3時くらいに出た時のやつですね。電気グルーヴがトップバッターで、ナンバーガールはその後に2番手として出た。吉村さん、随分と長いこと会場にいましたね(笑)。
吉村:あの時は途中でダウンして、一旦ホテルに帰ったんですよ(笑)。
加茂:話が前後しますけど、ブッチャーズと初めてご対面
した時、ナンバーガールのメンバーは凄く緊張してたよね。
吉田:そうですね。“あのブッチャーズと一緒にライヴをやれるなんて…”みたいな。ろくに口も利けなかったですね。
吉村:『〜DISTORTIONAL ADDICT』ができた時に、向井が手紙付きでサンプル盤を送ってくれたんです。その手紙はCDケースの中に一緒に入れて、今でも取ってありますよ。
吉田:いい話ですね(笑)。ブッチャーズとかイースタンユースには、向井君が「自分が手紙を書いて送ります」って言ってましたね。自分がリスペクトしつつ、ちょっと知り合いになれた人たちには自分から渡したいという想いが凄く強かったんですよ。
古閑:『〜DISTORTIONAL ADDICT』に関しては、もちろん“恰好いいなぁ”と思いながら聴きましたけど、自分のレーベルから出した『〜BYE
BYE』のほうがやっぱり愛着はありますよね。だから言い方は悪いですけど…(早口で不明瞭に)“こっち(『〜BYE
BYE』)のほうが恰好いいじゃん!”って思ってましたよ(笑)。と言いつつも、毎日大音量
で『〜DISTORTIONAL ADDICT』を聴きながら仕事してましたけどね。
──『DESTRUCTION BABY』以降、デイヴ・フリッドマンとレコーディングに取り組むようになってからはサウンドに変化が見られるようになり。
吉田:『DESTRUCTION
BABY』の時は、そこの現場にいた人間はみんな、そのサウンドの変化に心底ビックリしましたからね。デイヴのミックスを聴いて、“何でこんな音になるんだ!?”って凄く驚いた。
加茂:でも、福岡で8チャンネルのアナログで録っていた頃からニューヨークにあるデイヴのスタジオに行くまで、2ヶ月くらいしか実は間がないんです。だから、当時は急激な成長と変化を遂げていたんだと思いますよ。スリーター・キニーの最新作(『THE
WOODS』)もデイヴ・フリッドマンがプロデュースをやってますよね。デイヴのスタジオにナンバーガールのポスターが貼ってあって、それを見たスリーター・キニーが対バンしたことを覚えていたらしく、「ナンバーガールのあのクレイジー・サウンドをスリーター・キニーでもう一度やろうと思ってる」ってデイヴから昨年末にメールが来ましたけどね。
──吉村さんのなかでデイヴ・フリッドマンというプロデューサーはどんな位
置付けなんですか?
吉村:いわゆる“デイヴ・フリッドマン・サウンド”っていうのは個人的には好みではないかもしれないけど、ナンバーガール、フレイミング・リップスとは良かったんじゃないかな。あと、最近ではロウの新しいの(『THE
GREAT DESTROYER』)にはぶったまげた記憶があるですね。ナンバーガールとかは、“デイヴ・フリッドマン・サウンド”とはまた違うところで僕は買ってましたけどね(笑)。“ナムヘビ”の時は、ミックスが凄い凝ってるなぁ…っちゅうか、そう思いました。
「“向井コード”がバンドのサウンド・マジック」(加茂)
 ──下北沢SHELTERで東京初ライヴを行った日('98年3月12日『SMILEY'S
COLLECTION 〜新進気鋭〜』)のことは覚えていますか? ──下北沢SHELTERで東京初ライヴを行った日('98年3月12日『SMILEY'S
COLLECTION 〜新進気鋭〜』)のことは覚えていますか?
西村:余りよく覚えてないんですよね。“あれが初回かな?”と思ってたのが実は2回目のSHELTER('98年10月10日『PUSH
THE BUTTON #101010』)で、自分の企画でしたから。ちょうど前店長から店のブッキングを任され始めた頃で、凄くテンパってた頃だったので。
吉田:僕はとてもよく覚えてますね。ブッキングしたのは加茂で、スマイリー原島さんのところに話を持っていって。
加茂:吉田は福岡でメンバーにも会って、ライヴも観ていたんですけど、僕は生でナンバーガールを観たのがその日が初めてで。“何でこんなバンドが福岡から出てくるんだろう?”って思いましたよ(笑)。ヴォーカルはメガネで歯並びも悪くて(笑)、襟首が伸びたブルース・エクスプロージョンのTシャツを着て。ギターのひさ子ちゃんは下を向いて淡々と弾いてるだけだし、アヒト君はひたすらバカスカとドラムを叩いて、ベースの憲太郎君だけは唯一今風のミクスチャー・ロック兄ちゃんみたいな佇まい(笑)。キャラクターはバラバラだったにも関わらず、バンドとして妙な一体感があって、絶妙な絡み合いをしてましたよね。映画で言えばキャスティングが素晴らしい、と言うか。
吉村:そうそう、そこなんですよね。
──それを一言で表すと、さっき古閑さんが仰った“変わってるなぁ”という言葉に集約されるわけですね。
古閑:最初に観た時は“ヘン”でしたよ(笑)。もちろん、それと同時に“恰好いい!”とも思いましたけどね。
加茂:今でこそサンボマスターとか、あり得ないレベルのヴィジュアルっていうのが認知されてますけど(笑)、'98年の段階で向井君のあの予備校生風のルックスは相当なインパクトでしたよ。
西村:メガネがズレまくってたりとか(笑)。
加茂:ナンバーガールのライヴで初めてモッシュやダイヴが起きたのも、確かSHELTERですよ。
吉田:それはその日('99年4月14日『ムームー7』)の対バンだったデスサーフ2000のメンバーがダイヴしたからですよ(笑)。
古閑:あと、日本語の節回しが凄いと思いましたね。バックは当然洋楽チックなものなんですけど、あの日本語的な唄い回しがかなりオリジナルなものに感じましたよね。
吉村:そうなんだよね。真似しようと思ってもできないですよ。異様なんだよね、あの節回しが。
吉田:そう。凄くカラオケで唄いづらい(笑)。
加茂:コード感がヘンなんですよね。“向井コード”とでも言うような、どのコードブックにも載っていない彼独特の押さえ方をした不協和音になったりもするんですけど、それがナンバーガールのサウンド・マジックだということが後に少しずつ判ってくるんです。今でこそカポを使うロック・バンドも増えてきましたけど、当時は曲ごとにカポを替えるなんて本当にごく稀でしたよね。それと何より、当時から演奏が基本的に巧かった。驚きましたよね。
古閑:僕がブッキングをやってナンバーガールに出てもらったライヴでは、LOFTでやった『K.O.G.A
Records presents 九州音楽』('00年2月11日)が一番思い出深いですね。地獄の打ち上げが繰り広げられましたから(笑)。
西村:恐ろしい数の焼酎が消費されたという…(笑)。
古閑:最後は全員、記憶を失ってましたからね(笑)。
──初めて新宿LOFTに出演したのは、確かスリーター・キニーのオープニング・アクト('99年6月28日)でしたよね。
加茂:そうですね。LOFTが歌舞伎町に移転した直後で。
吉村:あれね、僕たちが断ってナンバーガールに話が来たんじゃなかったかな。
吉田:そうそう。ブッチャーズに断られて、イースタンユースはスケジュールが合わなくて、それでナンバーガールに話が回って来た。でも、お客さんは入ってなかったなぁ…(苦笑)。
──'90年代の終わり頃からくるりやスーパーカーといった日本語ロックの新しい風が吹き荒れましたけど、ナンバーガールはその急先鋒でしたよね。
吉田:語弊を恐れずに言えば“バンド・ブーム”と言うか、“下北ブーム”と言うか(笑)。
吉村:例えば呑み会の席とかで、ナンバーガールのメンバーはバンドとバンドのいい橋渡し役になってくれたんですよ。年齢の上も下も関わらずいいバンドをよく紹介してくれて、いい流れを作ってくれたんです。お客さんからは見えないところかもしれないけど、それが結果
としてはそのバンド・ブームみたいなものに繋がってると思いますね。
吉田:社交的と言うか、人見知りしないと言うか、誰とでもごく普通
に呑めるメンバーでしたからね。吉村さんや吉野さんのようにリスペクトしてる人と呑むと緊張はするんだけど、結果
としては5時間くらいずっと一緒に呑んでる、みたいなね(笑)。SHELTERやCLUB
Queで打ち上げをやっても、最後まで残るのは決まってナンバーガールのメンバー。あとは、3時過ぎくらいに現れる古閑さんくらい(笑)。
古閑:スイマセンね(笑)。いつだったか、僕が酔っ払って喋ってた時に向井君から「うるさいッ!」って怒鳴られたのは衝撃的でしたよ(笑)。その時はシュンとなりましたけど(笑)、いい思い出ですね。でもそれはさておき、上京したばかりのナンバーガールにとっては、呑み会の席での他のバンドとの交流って凄く重要だったんじゃないかと思いますよね。
吉田:確かに、呑みの席で知り合いは凄い増えましたからね。
加茂:“GUY呑み”とか“ビー酎”とか、東京では聞き慣れない九州カルチャーまで持ち込んでね(笑)。
古閑:九州人は一緒に酒を呑んだらみな友達ですから(笑)。
「『プールサイド』は僕らのオリジナルよりいい」(吉村)
 ──『OMOIDE
IN MY HEAD 2 〜記録シリーズ1〜』のほうには、ブッチャーズと共に回ったツアー“ハラコロ”(『HARAKIRI
KOCORONO』)からの音源('00年11月21日、長野JUNK BOX)も8曲収められていますね。 ──『OMOIDE
IN MY HEAD 2 〜記録シリーズ1〜』のほうには、ブッチャーズと共に回ったツアー“ハラコロ”(『HARAKIRI
KOCORONO』)からの音源('00年11月21日、長野JUNK BOX)も8曲収められていますね。
西村:俺のブッキング・ノートには、幻となった“ハラコロ”のツアー・スケジュールの詳細がずっと残ってますからね。
吉田:『NUM-無常の旅』の後に予定していたんだけど、解散が決まってできなくなったんですね。'99年から毎年11月にやって、4回目は幻。
西村:BEAの森(裕史)さんに「これいつやるんですか?」っていつか訊いてやろうと思って(笑)。
──“ハラコロ”ツアーをやろうと最初に声を掛けたのはどっちだったんですか?
吉村:向井だよ。ツアー・タイトルを決めたのもそうだし。“KOCORONO”は判るけど、なぜ“HARAKIRI”なのか?
っていうのが僕はずっと謎だったんですよ。
西村:SHELTERで観客席後方にビールケースを敷き詰めたのは?
吉田:あれは3年目。最後の“ハラコロ”ですね。後ろのほうのお客さんが見えづらいだろうと配慮した吉村さんのアイデアで。
西村:大変だったんですよ、あれ(苦笑)。あれ以降、あんなことやってないですから(笑)。
吉村:1年に1回くらいはSHELTERで新しい試みをやろうって言ってたんですよ。西村は当日になるまで本気にしてなくて、その日に僕が「何故ない?」って問い質して、それでようやく酒屋に走ったんです(笑)。お客さんが前のほうへ行くか、ビールケースのほうを陣取るか、どっちに行くか迷ってるのを見るのが面
白かったですね(笑)。ライヴハウスだと女の子って背伸びして観てるでしょ?
他のホールとかなら別にいいんだろうけど、“狭い空間のなかで違う見方はないものなのか?”っていう試みをやりたかったんですよね。
──SHELTERでの“ハラコロ”は特に、チケットも入手困難でしたからね。
吉村:店の周りにチケットを持ってないお客さんがたむろしててね。「吉村さん、どうにか入れませんか?」って言われて見るに見かねて、そのなかの男を捕まえて「この人たちにコーヒー奢れ」って、その時の全所持金2,000円を渡しましたよ(笑)。
──“ハラコロ”で一緒に回った時のナンバーガールのライヴはどうでしたか?
吉村:僕らメンバー全員が揃って人のライヴを観ることはまずないんですよ。それがあの時は、自然と3人とも観てましたからね。
吉田:ブッチャーズとツアーをやるたびに、メンバーは「ブッチャーズにはかなわないな」って言ってましたよ。「もっと頑張って存在感が出るようにならないと、ブッチャーズにはまだまだ及ばない」っていうような。「ブッチャーズの後にやるなんて考えられませんよ」っていう感じでしたよね。
吉村:途中から順番が変更になったんだよね。「別
に交互でもいいんじゃないか?」ってことになって。ナンバーガールも僕たちと一緒に回る頃には凄く勢いがあったし、お客さんも勢いがあったから、そういうところでは僕らもかなり気合いを入れてましたよ。
吉田:両バンドとも凄く気合いが入ってたから、本当にいいツアーだったと思いますよ。ナンバーガール・サイドから言うと、ブッチャーズの後にライヴをやるのは凄くやりづらかったんです(笑)。ブッチャーズの音圧と存在感にナンバーガールのお客さんも思い切り当てられちゃって。
吉村:凄く印象的なツアーでしたね、僕のなかでは。自分の調子が悪かったのは1回くらいで、その時に向井から「全部後に出たらどうですか?」って意見を受けたんですよ。
──『OMOIDE IN MY HEAD 2 〜記録シリーズ1〜』のラストには、ブッチャーズの「プールサイド」のカヴァー('01年6月24日、日比谷野外音楽堂『騒やかな群像』)が象徴的に収められていますね。
吉田:野音のライヴも凄く良かったし、「プールサイド」の演奏もいいので入れたいなと思っていて。「プールサイド」は実際のライヴでも後半に演奏されることが多かったし、エクストラ・ボーナス的な感じで最後に収めました。
加茂:ナンバーガールのカヴァーは同じコードですか?
吉村:キーが違うんじゃないかな。カポをしてるはずだから。向井はきっと、あのサビ前のコードが好きなんですよ。僕は向井が一人で「プールサイド」を唄ってるMTRの存在を知ってますよ(笑)。
吉田:いつから「プールサイド」をライヴでやり始めたのかはっきり覚えてないんですけど、リハの時に向井君から「『プールサイド』をやろうと思って…」と突然言われて。「エッ?
『プールサイド』? 何のこと?」って答えたら、「『プールサイド』は『プールサイド』ですよ」って返されて(笑)。“そんな曲、ナンバーガールにあったかな?”なんて一瞬思ったんです(笑)。
加茂:ラモーンズの「I Wanna Be Your
Boyfriend」やビーチ・ボーイズの「Do You Wanna Dance?」、フーの「So Sad
About Us」なんかもカヴァーしていたけど、日本のバンドの曲をカヴァーするのは初めてでしたからね。
吉田:イースタンユース経由で森田童子の「たとえば僕が死んだら」を向井君が個人的にカヴァーしていたことはありましたけど、基本的に“ヘタなカヴァーはやらない”っていうバンドだったので、ブッチャーズをカヴァーすると聞いた時はかなり本気度の高いカヴァーをやるつもりなんだなと思ったんですよ。改めて聴くと、本当にいい曲ですよね。メロディ・メーカーとしての吉村秀樹の凄さがよく判りますよね。
──カヴァーされたご本人としてはどうですか?
吉村:感激しましたよ、普通に。“僕らのよりいいんじゃない?”って思いました(笑)。それは本当に思ってる。
吉田:当時、何人かの関係者から「あれ、ナンバーガールの新曲ですか?
凄くいい曲ですね」って言われましたから(笑)。
加茂:サウンドも歌詞の世界観も、あそこまで違和感のないカヴァーも珍しいですよね。向井君が如何にブッチャーズから影響を受けているかはあの1曲に象徴されてると思いますよ。ブッチャーズとナンバーガールが出会うべくして出会った、凄く象徴的な曲ですよね。紛うことなき名演ですね。
──そう言えば、『SAPPUKEI』収録の「ABSTRACT TRUTH」に“禅問答/吉村秀樹”という歌詞がありますが、ご当人はこの曲を聴いた時にどう思ったんですか?(笑)
吉村:ご当人はですね、何も知らされてなかったんです。CDを聴いてしばらくして「……俺じゃん!」って(笑)。メンバーの誰も、それまでに何も教えてくれなかったんですよ(笑)。
「4人全員が替えの利かないメンバー」(吉田)
 ──こうして改めてライヴ音源を聴くと、つくづく生粋のライヴ・バンドだったんだなと痛感しますね。 ──こうして改めてライヴ音源を聴くと、つくづく生粋のライヴ・バンドだったんだなと痛感しますね。
吉田:そうですね。ライヴをやるのはごく当たり前のスタンスでやっていたし、“ライヴをやらないで何のためのバンドか!?”みたいな心持ちでいましたからね。時にはライヴのほうがレコーディングしたものより良かったこともあったから、痛し痒しですけど(笑)。
吉村:彼らのライヴでよく覚えているのは、ライヴ盤(『シブヤROCKTRANSFORMED状態』)にもなった渋谷のクアトロの時('99年10月1日)ですね。メンバーが全員クッタクタで、そのクッタクタな状態が後ろノリになってて、照明は暗かったんだけど音は凄い良かった。だからあの演奏がライヴ盤になったのは嬉しかったのを覚えてます。あのノリはちょっと特別
だったと思いますね。絶妙なタイム感もあったと思うし。
加茂:初めてのクアトロで、チケットはソールドアウトで、巷の評判も上がってきていて、気合いの入り方は尋常じゃなかったですからね。チューニングの甘さやミスもよく聴けばあるんですけど、それも記録のひとつなんだという発想は今回のBOXにも繋がってますよね。
吉田:そう、凄くドキュメンタリー的要素の高いバンドでしたからね。
西村:常に加速していたバンドでしたよね。立ち止まる瞬間がなかったと言うか。まぁ、憲太郎さんとは途中から普通
の呑み友達になりましたけど(笑)。
吉田:その“立ち止まらない感”っていうのは、向井君の性格によるところが大きかったでしょうね。
加茂:そうだね。音楽に関しては一切の妥協を許さないからね。
古閑:バンドが東京に出て来た初期の頃から携わってた僕らにおいては、その加速感に付いていけなかったですから(笑)。イヤな言い方になりますけど、“いつまでも僕らのそばにいてほしかった”みたいな部分もあるじゃないですか。でも、そんなことお構いなしにドンドンドンドン先に行っちゃった、っていう感覚が凄い強くて。彼らの音楽に付いていけなかったという意味じゃなくて、その姿勢にね。それが正直なところかもしれないですね。
吉村:この音源を聴いていくとね、メンバーの絶妙な感じというのがオリジナル・アルバムよりももっと強く感じると思いますよ。
吉田:そうですね。あの4人が揃ってこそのナンバーガールだったんです。全員、替えの利かないメンバーだったんですよ。初めてSHELTERでライヴをやった頃から、タイトロープの上を渡っているような緊張感がバンド内にはあって、デビューする前から“いつ解散してもおかしくないな”って僕は思ってたんです。それが最後は思っていた通
りになっちゃったんですけど…。
──もしあの時ナンバーガールが解散していなかったら、今頃どうなっていたと思いますか?
吉田:うーん。“ナムヘビ”の後にもう1枚アルバムを作ったかもしれないですけど、そこで終わってたかもしれませんね。解散は'02年11月ですけど、'03年には終わっていたかもしれないです。
吉村:『荒野ニオケルbloodthirsty
butchers』をレコーディングしてる時に、向井から「ナンバーガール、解散することになりました」って電話を貰った時の落ち込みったらなかったですよ。“ハラコロ”の予定もあったからね。
古閑:いいバンドっていうのは大抵生き急いじゃうんですよね。ナンバーガールの解散を聞いた時も、“やっぱりそういうものなのかな?”って思いましたね。もちろん、長く活動を続けるいいバンドもたくさんいるんだけど、ナンバーガールの場合は短いほうに分類されるのかな、って。まぁ、短いって言ってもオリジナル・アルバムは4枚、ライヴ盤を含めたら6枚も出してるわけだから、決して少ないわけじゃないですよね。
西村:世間的には短命だったイメージがありますけどね。SHELTERに出てるバンドでも「ナンバーガールが好きだった」っていう人たちが凄く多くて、「ああいう恰好いい音楽を長く続けたい」って言いますね。
吉村:多いよね、そういうフォロワーみたいな人たちがね。でもね、ナンバーガールは音楽的にそういうバンドとは全然違うんですよ。微妙なポップ感がありながら、実はポップじゃなかったりするんです。その不思議な魅力ですよね。
吉田:基本的に向井君はポップなものが好きなんですよ。できるだけポップな形に作り上げたいという欲求が彼には凄くあったから、妙なポップ感…ナンバーガール的ポップ感があったんでしょうね。他の人にはできないような独特なことをやってたバンドだと思うんですよ。そういうのが“オリジナリティがある”と言っていいと我々は思っていたので、だからこそ僕らはナンバーガールのスタッフで在り続けることが凄く楽しかった。まぁ、大変なことも多々ありましたけど(笑)、やっぱり凄く面
白かったですよ。
──若いリスナーのなかには、“ZAZEN BOYSの向井秀徳しか知らない”という人がぼちぼち増えているみたいですけど。
吉田:そうですよね。ナンバーガールは当時の中高生には判りづらくて、でも20〜30代の人にはハード・ヒットするような音楽だったんじゃないかな。
吉村:ヘンな悲壮感を…悲壮感って言うのかな、ドロップアウトとも違うし。でも、そんなようなものを引き上げたバンドだと思いますよ。世代も性別
も関係なく、聴いてる人たちの心を掴んだバンドだと思いますね。○○感っていうのは語弊があるかもしれないけど、その音楽と、ポップ感と、歌詞と、バンドの名前と佇まいでそれを掴んだっていう。まとめて言うとポップってことなんですけど、それは凄く思いますね。
加茂:子供の頃に聴いたレッド・ツェッペリンでもセックス・ピストルズでもそうだし、最初は理解不能じゃないですか。“何じゃこりゃ!?”っていうような。自分はその音楽に感動してるけど、分析不能に陥る瞬間ってロックの基本だと思うんですよ。ナンバーガールはそういったロックの基本である衝撃があった。音は悪いし、歌も叫んでるだけだし、写
真を見るとヴォーカルは予備校生みたいだし(笑)、でも感動してる自分が確実にいるという。それがナンバーガールというバンドだった気がしますね。長いことこの仕事をやっている僕でさえ、ナンバーガールの音楽と出会った時は分析できない凄さを感じてましたから。
古閑:そんなナンバーガールを引っ張ってきた加茂さんは凄いと僕は思いますけど。
加茂:いやいや。「omoide in my head」を初めて聴いた時も、最初からコード感が普通
とは違うと思いましたよね。“タイトルはバズコックスの「Harmony In My
Head」からかな?”とか、ニール・ヤングやあがた森魚の引用があったりとか、ロック的な語彙の引っ張り方がちょっと尋常じゃないなとは思いましたよ。それはジャケットだけ見ても、発信してる力が違いましたからね。
「『IGGY POP FAN CLUB』なんてタイトルを付けるセンスが最高」(西村)
──向井さんはZAZEN BOYS、ひさ子さんはブッチャーズとtoddle、憲太郎さんはSloth
Love Chunksやタイガン、SPIRAL CHORDなどで活躍中で、アヒトさんに至っては…。
古閑:ヴォーカルまでやってますからね(笑)、VOLA
& THE ORIENTAL MACHINEとして。全員が中心人物になれるメンバーがたまたまナンバーガールとして集まったってことでしょうね。
吉村:でもね、“僕にもできるんだ”とか“私もしっかりしなくちゃいけない”とか、その意識を引き上げたのは間違いなく向井なんですよ。だからこそ、今はみんなそれぞれやってるじゃないですか。
吉田:ひさ子ちゃんも今度のブッチャーズの新作(『banging
the drum』『bloodthirsty butchers VS +/−{PLUS/MINUS}』)で唄ってますもんね。
吉村:ひさ子がメイン・ヴォーカルのtoddleも今録ってるし。僕も何らかの形で関わると思いますけど。
──最後に、いささか“ABSTRACT TRUTH”(抽象的な真実)な問いになってしまうんですが(笑)、みなさんにとってナンバーガールとは?
古閑:バンドって何が起こるか判らないっていうのを、彼らと接して実感しましたね。僕がこの業界にいて20年、そんなことを改めて思い知らされたバンドです。数字的にも音楽的にも、すべてが極限にまで出たバンドだと思うし、だからこそ寿命が短かったのかもしれないですね。それが刹那的だったのかどうかは判りませんけど、何度も申し上げて恐縮ですが…僕個人としては儲けさせて頂きました、ハイ(笑)。
西村:「IGGY POP FAN CLUB」なんてタイトルを付けて曲にするような、あのセンスが最高でしたよね。歌詞には“IGGY
POP”なんて一言も出てこないのに(笑)。あとは、自分が小屋の人間だからっていうのもありますけど、いい呑み会をするバンドだったな、と。向井さんを筆頭に、酒を呑むのがごく日常的と言うか、恐らく人生の半分以上は酒を呑むことで占められていると言うか(笑)。今も向井さんはフラッとSHELTERに現れて呑みに来てくれることもあるし、有り難いですよ。
吉田:まぁ…呑みましたねぇ、ホントに。よく呑んで、よく喋ったなぁ(笑)。本当に、自分の人生のなかでもの凄く重要な位
置を占める存在だったと思いますよ。当時は彼女もいなかったし(笑)、ナンバーガールに賭けるしかないところもあって(笑)。
加茂:ナンバーガールと出会う前の吉田は、本当にダメ人間の極致だったもんね(笑)。
吉田:まぁ、もともとがダメ人間でしたから(笑)。でも、自分の趣味と仕事がたまたま一致した幸運な例だと思いますよ。自分でも感情移入しすぎるくらいだったと思いますから。
吉村:吉田さんは一時期僕らの面倒も見てくれていて、本当に世話焼きですからね。
加茂:僕個人としては、メジャーっぽいあらゆる既成の価値観が一度ひっくり返されましたね。メジャーの判りやすい方程式だけじゃないんだな、と。ナンバーガールと出会うまでに10年以上この世界にいて、“メジャー・デビューするならいいスタジオに入っていい音で録ろう”とか“事務所も大きいところに入らせよう”とか、業界的なルーティンに自分が毒されていたところにナンバーガールが目の前に現れた。リアリティがあれば8チャンネルのアナログ・レコーディングでもいい、事務所なんてなくたっていい、スタイリストもヘアメイクも要らない。ただ単純にバンドを恰好良く見せられればいいんだと思うようになったんです。向井君はやっぱり主義・主張が強いから、彼を任せられる事務所はなかなかないだろうなとも思ったしね。根本的なDIY精神をよく理解していたバンドだったし、ロック・バンドというのはやっぱりこう在るべきだな、と。それは今の向井君のスタンスにおいても変わらないし、端から見ていて僕は今は凄くよく理解できますよね。
吉村:僕はですね、やっぱりキーポイントは“生ビール”ですね(笑)。そういうところが言葉にするなら“男らしい”し、本当に素晴らしかったと思います。あとは、今もメンバーそれぞれが確固たるポジションで動いているし、みんな個性がありますね。ナンバーガールに関しては絶妙たるその瞬間が合わさってたんじゃないか、っていう。向井のいろいろな判断も正解だったし、彼の感性も素晴らしい。先にあるヴィジョンとか決断力とか、凄いんですよ。それに尽きますね。バンドが上り調子だった時に向井が解散を決断したのも、結果
としては凄いことですよ。
吉田:そう、憲太郎君の替わりをあえて見つけようとしなかったのは凄いですよ。
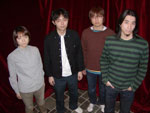 吉村:だって、「福岡市博多区から参りました、ナンバーガールです」ということを最後まで守り抜いたじゃないですか。違うメンバーが加入したらそれは違っちゃうわけで。だから向井のこだわりは凄いものだったと改めて思いますね。僕も勉強になったし、その瞬間を見れたことは良かったですね。自分はバンドを持続させているし、ナンバーガールの元メンバーもいるし、違う感情はありますけど。まぁでも、ホント喉ごし爽やかな“生ビール”みたいだった。いろいろゴタゴタと話をしてきましたけど、僕はナンバーガールを全部そういうふうに表現しますね。要するに、“ナンバーガール、どうもありがとう”ってことですね。 吉村:だって、「福岡市博多区から参りました、ナンバーガールです」ということを最後まで守り抜いたじゃないですか。違うメンバーが加入したらそれは違っちゃうわけで。だから向井のこだわりは凄いものだったと改めて思いますね。僕も勉強になったし、その瞬間を見れたことは良かったですね。自分はバンドを持続させているし、ナンバーガールの元メンバーもいるし、違う感情はありますけど。まぁでも、ホント喉ごし爽やかな“生ビール”みたいだった。いろいろゴタゴタと話をしてきましたけど、僕はナンバーガールを全部そういうふうに表現しますね。要するに、“ナンバーガール、どうもありがとう”ってことですね。
|








 ──まず、2枚組ベスト『OMOIDE
IN MY HEAD 1 〜BEST&B-SIDES〜』から始まった“omoide in my head project”が始まった経緯から訊かせて下さい。
──まず、2枚組ベスト『OMOIDE
IN MY HEAD 1 〜BEST&B-SIDES〜』から始まった“omoide in my head project”が始まった経緯から訊かせて下さい。 ──吉村さんのナンバーガールとのファースト・コンタクトというのは?
──吉村さんのナンバーガールとのファースト・コンタクトというのは?
 ──下北沢SHELTERで東京初ライヴを行った日('98年3月12日『SMILEY'S
COLLECTION 〜新進気鋭〜』)のことは覚えていますか?
──下北沢SHELTERで東京初ライヴを行った日('98年3月12日『SMILEY'S
COLLECTION 〜新進気鋭〜』)のことは覚えていますか?  ──『OMOIDE
IN MY HEAD 2 〜記録シリーズ1〜』のほうには、ブッチャーズと共に回ったツアー“ハラコロ”(『HARAKIRI
KOCORONO』)からの音源('00年11月21日、長野JUNK BOX)も8曲収められていますね。
──『OMOIDE
IN MY HEAD 2 〜記録シリーズ1〜』のほうには、ブッチャーズと共に回ったツアー“ハラコロ”(『HARAKIRI
KOCORONO』)からの音源('00年11月21日、長野JUNK BOX)も8曲収められていますね。
 ──こうして改めてライヴ音源を聴くと、つくづく生粋のライヴ・バンドだったんだなと痛感しますね。
──こうして改めてライヴ音源を聴くと、つくづく生粋のライヴ・バンドだったんだなと痛感しますね。
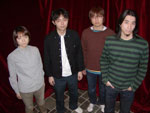 吉村:だって、「福岡市博多区から参りました、ナンバーガールです」ということを最後まで守り抜いたじゃないですか。違うメンバーが加入したらそれは違っちゃうわけで。だから向井のこだわりは凄いものだったと改めて思いますね。僕も勉強になったし、その瞬間を見れたことは良かったですね。自分はバンドを持続させているし、ナンバーガールの元メンバーもいるし、違う感情はありますけど。まぁでも、ホント喉ごし爽やかな“生ビール”みたいだった。いろいろゴタゴタと話をしてきましたけど、僕はナンバーガールを全部そういうふうに表現しますね。要するに、“ナンバーガール、どうもありがとう”ってことですね。
吉村:だって、「福岡市博多区から参りました、ナンバーガールです」ということを最後まで守り抜いたじゃないですか。違うメンバーが加入したらそれは違っちゃうわけで。だから向井のこだわりは凄いものだったと改めて思いますね。僕も勉強になったし、その瞬間を見れたことは良かったですね。自分はバンドを持続させているし、ナンバーガールの元メンバーもいるし、違う感情はありますけど。まぁでも、ホント喉ごし爽やかな“生ビール”みたいだった。いろいろゴタゴタと話をしてきましたけど、僕はナンバーガールを全部そういうふうに表現しますね。要するに、“ナンバーガール、どうもありがとう”ってことですね。