ネイキッドのオープンから早3ヶ月……
 |
ネイキッドロフトが無国籍の街・新宿百人町にオープンしてもう3ヶ月が過ぎようとしている。
お客さんの動員力は少ないが凄い表現者を私はたくさん知っている。しかしお客が少ないとお店の存続事態が危機に陥るから、なかなか出演して貰うことが出来ないのだ。
これは私の長い経験上から言うのだが、動員20〜30人ぐらいの人達のライブが一番面白いと思っている。でもそんな表現者に出会うことがなかなか出来ない…現在のロフトグループの空間創造状況に苛立っていた。そんな苦悩(?)の中からこのネイキッドロフトのアイデアは生まれたのだ。
この空間はライブのお客さんが20〜30人でも、表現者に一切のノルマや金銭的負担なしにお客さんの好奇心を満足させ、店側も表現者もちゃんと明日という希望を持ち、かつ店も潰れないような体制を作ろうという画期的なコンセプトを持って生まれた空間なのだ。
だから今のところネイキッドロフトは以前のプラスワンのごとく、会社(ロフト)の経理部門からの圧力なしに、赤字でも平気で運営できるところに最大の魅力がある。
赤字続きのプラスワン時代(開店してから2年は赤字だったな)は、私が会社に対して突っ張りきって、ロフトとかシェルターの利益を生まれたばかりのプラスワンにつぎ込んでいたから何とか潰さないで存続出来た。しかし今回のネイキッドの店長は九州男児で弱冠28歳のテツオだから、“赤字”を出すことの風当たりはそれなりに強いらしい。まぁ、ブッキングのほうは各店のスタッフによる協力もあって、勿論赤字だがそれなりにお客は入っているようだ。
さて、問題はテツオ店長始めスタッフが一番力を入れている“オープンマイクデイ”が不振の極まりというか、限界点を超えているのだ。
この企画は、毎週火曜日の6時30分から10時30分までステージとマイクを解放して、音楽でもトークでも、秘蔵ビデオやDJでも何でも表現して貰って、みんなで楽しもうという企画なのだが、これが見事にこの企画に出演を希望する表現者が来ないのだ。勿論、お客さんもまるっきり来ない。
3月9日に行われた『第7回オープンマイクデイ』などは、それはひどいものだった。8時を過ぎてもお客ゼロ、出演者ゼロ。ライブタイム終了の10時30分までに登場した出演者は何とか3人、お客さん4人(この表現者を入れてだ)であった。スタッフは街角で歌っている連中にも声をかけ、宣伝も頑張ってしたはずだったのだが…。
緊急深刻トークショー 〜
どうする! どうなる? オープンマイクデイ(笑)
…出演:平野 悠(テツオ店長教育係)&テツオ店長
仕方がないので、私はテツオ店長と緊急深刻公開トークを開いた。勿論、客は誰もいない。聞いているのは手持ちぶさたの店員だけだ。
この日、ネイキッドロフトは史上最悪の売り上げが予想された。新宿ハローワーク前の監視カメラも、この寒空の中なぜか寂しそうだったな(笑)。
「テツオ、このオープンマイクデイでの君の理想は判るけど、まず毎週開催というのはやはり無理なんじゃない?」と私は酒も引っかけてテツオ店長に迫る。
「ハイ、僕も困っています。こんな表現者に心優しいイベントはないと思うのだけど、どうして誰も来てくれないんでしょうかね? 悠さん解説して下さい。僕、この企画は自信あったんですけどね…。だって、この街角の寒空でギターを抱えて歌っている人達とか、悠さんがよく言う、街の片隅に生息している、それぞれのこだわりを持ったいぶし銀の無名の人達なんかにはとても親切じゃないですか。確かにノー・チャージだし、ギャラは出ないけれど、お客さんからカンパも請求できるし、一応PAもしっかりしていて…」と今にも泣き出しそうである。
「う〜ん、大丈夫だよ。もう10年も前になるけど、プラスワンの開店時に売り上げ一日600円という金字塔があるし、その記録はそうは簡単に破ることが出来ないと思うよ。でもこのまま朝までお客ゼロだったら面白いよね」と私はテツオ店長のフォローに入った。
「そんなこと誰も聞いてませんよ。からかうのはやめて下さい。悠さん、今日は一番高いボトルを入れて下さいね」と真っ赤に怒ったテツオ店長。
「この企画は、ただ出演して貰って後はほったらかしにするのではなくって、店としては表現場所のない新人を発掘したいって思って、ちゃんと出口(デビュー等)まで用意しているしね。今日なんか来れば1時間はステージを占拠して演奏できるよ。カラオケより安いし…なぜ誰も来ないんだろうね?」
「やはり、至れり尽くせりではダメなんですかね?」
おっとっと、テツオ店長はやけっぱちになってきたぞい。
「どっちにしても、俺の長いライブハウス経営の経験から言うと、日本人はたとえ無料でも無名な表現者の演奏なんかを聴くことはほとんどあり得ないよ。その昔、『ぴあ』なんかの情報誌がなかった時代には、お客が足を棒にして何とかライブ会場を探し当てて来てくれて、とにかく日本のロックを聴きたいっていうことで、どんなに無名なバンドでもそれなりにお客が入った時代はあったけど、今の時代ではダメなんでないの? そんな酔狂な客はいないよ」と私は答える。
「でも80年代のパンク・ムーブメントの時代は、ほとんど無名なバンド群をあれだけ多くの人がお金を払って聴きに来てくれた時代もあったわけでしょ?」とテツオ。
「う〜ん、あれはお祭りだったからだと思うよ。その頃パンクの情報量があまりにもなかったんで、パンク・ファンはとにかく足を運んで観に来るしか方法がなかったからね。それにしても、今まで7回このイベントを続けているんだけれど、みんな一人で来るね。友達がいないか、友達に聴かせたくないんだろうか? どうしてだろう? それで自分の演奏が終わるとすぐ帰ってしまう。何とか盛り上げてやろうといった気持ちがまるでない」
「偉そうな言い方かもしれませんが、もし自分だったら、ライブハウスでパフォーマンスするっていう日には友達の2、3人は必ず誘いますけどね。だって観てもらいたいじゃないですか…そうでもないんですかね? 確かにノルマはないのだけど、ステージに立つっていうことは人に観てもらうことなのだから、表現者は表現者で心のノルマとでもいいますか…うーん、難しいですね(涙)」
さて、いかに推移するのかネイキッド・オープンマイクデイ…目が離せないぞ。
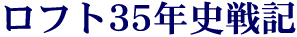
第2回:烏山ロフト編 (1971年〜72年)
お客さんは私のいい音楽教師であった
 |
私はジャズ喫茶・烏山ロフトでお客さんの数々から自分の知らないロックやフォークを教えて貰った。それはちょっと極端かもしれないが、私はビートルズすら興味がなかった。だからいわゆるロックやフォークというものを全然知らなかった。まだいわゆる革命運動をやっている時にベ平連を中心とするフォーク・ゲリラにも新宿西口で何回か遭遇したし、三里塚の農民の青年行動隊が始めた「日本幻野祭」や「中津川フォークジャンボリー」などが開催されていたのは知っていたが、まさか歌や踊り(歌舞音曲)で革命が出来るとは思っていなかった。私は職業革命家を目指していたわけだし、だから若いお客さんは自分にとって先生でもあった。「悠ちゃん(私は当時いつもそう呼ばれていた)、ビートルズも知らないの?」と呆れられてもいた。ということは、私は数々のお客さんの優しさに“はぐくまれ育てられていった”と言ってもいい気がする。
私が初めてロックに興味を持ったのは、当然お客さんの影響もあってだが、世界のジャズの主流がいわゆるCTI系(当時イージーリスニング・ジャズなどと言われた)のチック・コリアとかフュージョン系(ジャズとロックの融合?)になっていくのをイライラしていた時期でもあった。そんな不確かで堕落してゆくジャズに反吐が出ていた時期でもあったが、私の音楽の聴き方や価値観が180度変わる事件が何度も何度も烏山ロフトであったのだ。
それは、ある常連客がピンク・フロイドの新盤『原子心母』を聴かせてくれてからだと思う。このプログレ(?)LPには少なからずブッ飛んだ。「へ〜、ロックって意外と面白いじゃん」と思ったのが最初だった。次にエマーソン、レイク&パーマー(EL&P)の『展覧会の絵』がかかった時にはもう間違いなく驚嘆していた。更には自分にとって一番苦手な“フリースタイル・ジャズ”の山下洋輔トリオの『ダンシング古事記』(これもお客さんが持ってきてくれたものだ)を聴いてジャズの認識が変わり、友部正人の『にんじん』にショックを受け、最終的なとどめは小坂 忠が歌う“エイプリル・フール”だった。
そしてしばらくすると、私は日本のロックやフォーク・ソングにも興味を思った。それまでほとんどジャズしか聴かなかったし、その他の音楽を馬鹿にしていたのを悔い改めた。私はロックやフォークのレコードの蒐集も始めるようになった。アングラの帝王・浅川マキや三上 寛を聴いて「こりゃ〜参った!」と思った。はっぴいえんどの何か怪しげな巻き舌で歌う日本独特のロックにもしびれていった。だからギリギリ潰れる寸前の吉祥寺「OZ」のライブには何回も足を運んだものだった。当時の「OZ」や渋谷「GYB」はいつ行ってもガラガラでお客は極端に少なかったし、何かとても荒んでいて、まさに終わってしまったヒッピー文化の連中がロックをやっているに過ぎないと感じていて、まさか私が彼らの意志を引き継いで“ライブハウス経営”をするなんて最初は考えもしなかった。
吉祥寺「がらん堂」の衝撃
71年に開店した烏山ロフトは7坪あまりのほんの小さな店である。15人も入ると一杯になってしまう。昼間は音楽喫茶をやり、夜は朝4時まで酒場をやった。お客は貧乏な若者達ばかりの世界であった。だから自ずから売り上げには限界があった。
私はやっと勝ち得たこの小さな空間をとても愛していた。友達以上の付き合いまで出来る素晴らしいお客さん達にたくさん恵まれた。店の成り行きを一緒になって心配してくれる常連達。私はこの時期、幸福だった。毎日が楽しく、売り上げは順調に伸び、店内は満員の日が続いた。毎月レコードを買うことも出来、店員にも滞りなく給料を払うことが出来、レコードのストックも増えていった。「自分はこういった仕事で将来も生活してゆくんだ」と心新たにし、この仕事が天職にも思えた。
しかし、将来的展望というところまで考えると、この7坪の小さな店だけではとても未来に対する明るい展望を持つことが出来ないと感じていた。私や従業員の家族が食べてゆくのには不安もあり、不十分であった。烏山ロフトは烏山では有名になり、更には遠くから来てくれる客まで増えていったが、自分としては若干不満だった。
私はそんな頃、中央線吉祥寺の音楽文化とでも言うか、新しくわき起こって来た若者文化にとてもはまっていた。吉祥寺には烏山からバス一本で行くことが出来た。ジャズ文化は吉祥寺の一つの名物にもなっていて、多くの若者がこの街にやって来た。数万枚のレコード・ストックとJBLパラゴンという日本で一番巨大なスピーカーを擁するジャズ喫茶「ファンキー」を筆頭に、吉祥寺ジャズ道場「メグ」というおっかない店もあったし、洋楽だけど当時流行りのレッド・ツェッペリンやストーンズなんかをガンガン巨大な音で流す「赤毛とそばかす」なんかをこの目で見てぶっ飛んでいた。こういった店はいつも若者で超満員であった。『名前のない新聞』といったミニコミ誌は中央線吉祥寺発であり、当時の閉塞状態な若者の心を捉えていた。
しかしその中でも一番気に入っていたのは、規模も設備投資もそれほど必要でなく、私でも何とか実現出来そうな“とある店”だった。それが私に2店目の店舗の出店を決意させてくれた「がらん堂」である。この店は吉祥寺の外れの小さなビルの2階にあった。この店は規模も小さく(多分20坪ぐらい)、基本的には日本のフォーク・ソングや日本のロックを流す特異な店であった。この時期、巷ではフォークやロックに関しても洋楽が主流であったし、中津川であった「フォークジャンボリー」の熱気もみんな忘れたように関係なかったと思えた時代だ。何かこの店だけがその熱気というかプロテスト・ソングの思想を引き継いでいるんだなと思った。これにはとても感激した。
「がらん堂」では毎夜何の前触れもなく友部正人や高田 渡、南 正人、シバ、中川五郎といった中央線沿線に住んでいるシンガー・ソングライターが夜な夜なギターを抱えてやって来て突然歌い出し、そして店内に居合わせたお客さんと一緒に歌い出すのだった。高田 渡の「自転車にのって」なんかを合唱するのだ。「猫まんま」という食事が面白かった。マイクも、照明も、ステージもなく、特別な料金もなかった。思わず「これは凄い!」と唸り、もしかして自分の次の展開にそんな形の店を作ることが出来るかもしれないと思い続けていた。それはまるで私が高校時代に通った店のような、どこか政治文化の匂いがするカウンター・カルチャー的な雰囲気がかすかに支配していた感じがあった。
当時渋谷に一軒だけあったライブハウス「BYG」がなくなり、吉祥寺にほんの束の間開店し営業していた「OZ」が閉店していた。これで都内にはライブを聴くことが出来る店は一軒もなくなってしまった。それほど日本のロック系の音楽事情が冷え込んでいたのだろうか。当時は歌謡曲が主流だった。常時ライブをやっている空間が東京にはなくなり、日本のロックやフォーク・ファンは年に数回開かれる日比谷野音なんかのフェスティバルに行くしかなかったのだ。(次号に続く)
※この物語は、現在私が書き続けている『ロフト35年史戦記』のオムニバス版(抜粋)です。
私は今、ロフトの35年にもわたる歴史を書き続けている。記憶は現に古ぼけていて、そして私は昔のロフトを思い出すたびにそれぞれの“一期一会”の運命に感謝の気持ちを持ちつつ、痛切に感じている。貴重な出会いと別れ、恥ずかしくってのたうち回るような思い出もたくさんありすぎるのを、私は“忘却の彼方”から思い切り良く引っ張り出している。
春の訪れは万人にとてつもない活力を生み出してくれると信じて……「生きているって言ってみろ!」ってどこかで誰かが叫んでいる空耳が突然鳴った。
ロフト席亭 平野 悠
|
